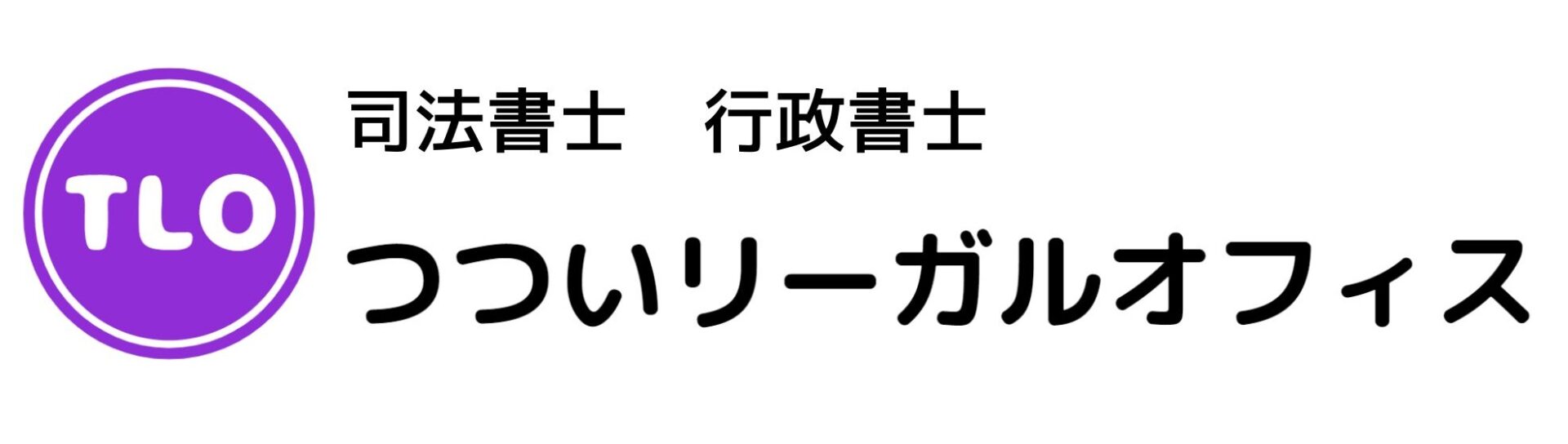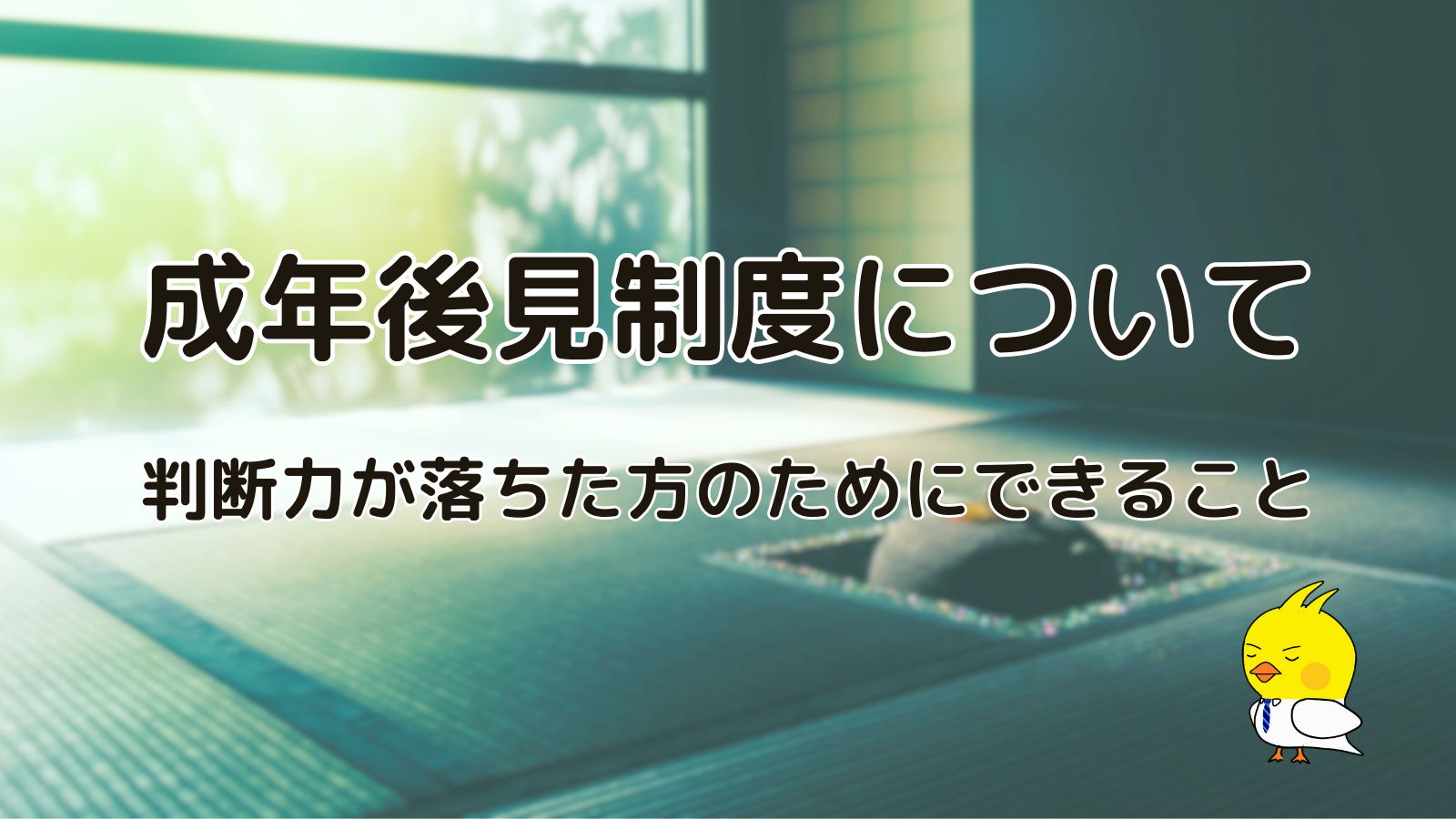成年後見制度について
認知症などで判断能力が衰えると、不動産の売却や遺産分割協議への参加など、財産の管理や処分ができなくなります。
また、日常生活においても、詐欺などの犯罪に巻き込まれたり、親族や家に出入りしている人が勝手にご本人のお金を使ってしまうというおそれもあります。
このような状況のために、成年後見制度があります。
司法書士 行政書士つついリーガルオフィスでは、成年後見の申立て、成年後見人業務を行っています。
成年後見制度が必要になる場合
成年後見制度は、判断力が落ちた方に次のような行為が必要な場合に申立てされることが多いです。
- ご自宅を売却する必要がある。
- 相続人となり、遺産分割協議に参加する必要がある
- 財産管理や身の周りの世話をする親族等がいない
- 賃貸不動産などの管理のために、契約等の法律行為を行う必要がある
- 財産管理を、第三者に行わせたい
成年後見制度の種類
成年後見制度には、判断能力の程度により、次のような種類があります。
補助
日常生活は行えますが、不動産などの重要な財産の管理や契約行為がやや困難な場合です。
補助開始の審判により補助人が選任され、ご本人の同意に基づき付与された同意権や代理権の範囲で、ご本人をサポートします。
保佐
日常生活は行えるものの、契約の内容を理解・判断することが非常に難しい場合です。
保佐開始の審判により保佐人が選任され、重要な財産行為の同意、ご本人の同意により付与された代理権の範囲でご本人をサポートします。
後見
物事を判断することができず、契約の内容を理解・判断することができない場合です。
後見開始の審判により成年後見人が選任され、日用品の購入など日常生活に関する行為を除いて、すべてにおいてご本人を代理します。
成年後見人の役割
成年後見人の役割
成年後見人は、本人の資産が失われないよう財産管理の支援を行います。
さらに、重要な財産の処分などを行う際には、本人の意思を支援して法律行為の同意や代理を行います。
また、施設やケアマネージャーの支援のもとに、本人の日常生活における適切なサービスが受けられるよう支援を行います。
成年被後見人の財産管理
後見人は、ご本人の財産を適切に管理するために、具体的には次の支援を行います。
- 預貯金の入出金を管理し、必要な費用の支払い
- 所有している不動産の管理、資産状況から必要とされる場合は売却
- 納税や税申告の手続き
- 各種支給金の申請、受領
なお、上記の財産の管理がきちんと行われているか、家庭裁判所に定期報告することが義務付けられています。
成年被後見人の身上保護
後見人は、ご本人の日常生活を支援するために、身上保護として、具体的には次のような支援を行います。
- 施設の入所や退所などの契約や手続き
- 介護認定や、介護サービス事業者との契約や手続き
- 定期的に施設を訪問するなどにより、状況に変化がないかの見守り
身上保護にはご本人の親族など、財産管理を行う後見人とは別の後見人が選任されることが多いです。
被補助人、被保佐人の同意や代理
後見人は、ご本人に代わって日常生活に必要な行為以外の各種法律行為について、本人に同意したり、代理します。
具体的には、次の法律行為の代理、同意を行います。
- 金銭の借り入れ、保証
- 不動産その他重要な財産の売買
- 贈与をすること
- 相続の承認、相続放棄、遺産の分割
- 建物の新築や増築
これらの行為を本人が行った場合、または同意を得ないでした行為は取り消しができます。
本人が行えるのは、日用品等の購入に限られます。
成年後見制度の利用に当たって
気を付けたいこと
法定後見および任意後見制度の利用には、次の点に注意が必要です。
- 申立人が本人以外の場合、財産の使用などについて、申立人の考え通りにはいかない可能性があります
- 不動産の売却や遺産分割協議を目的に後見を申し立てた場合でも、一度開始された後見はずっと継続されます
- 司法書士や弁護士などの第三者後見人に対しては、毎年ごとに家庭裁判所が定める報酬を支払う必要があります
- 後見人に選任されると、家庭裁判所に財産の変動、収支や心身の状況を定期報告する義務が生じます
- 支援信託を目的とする申し立ての場合でも、財産状況などによっては支援信託ではなく、後見が継続します
法定後見制度と任意後見制度の違い
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度
法定後見とは、家庭裁判所に後見の申し立てを行い、家庭裁判所から選任された後見人によって後見が開始します。
判断力が低下した後に申し立てを行います。ご親族が申し立てるケースが一般的です。
任意後見制度
任意後見とは、後見状態になった場合に備えて、しっかりしたうちに後見人に何をお願いするかを決めて公正証書で契約書を作成し、後見状態になった場合に、契約における後見人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることによって、後見が開始します。
判断力が低下する前に契約書を作成する必要がありますので、早めの対応が必要になります。
成年後見制度の利用方法
成年後見制度を利用するためには、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
申立人は、本人、配偶者、四親等内の親族です。
ただし場合によっては、市区町村長など第三者が申立人になることもあります。
任意後見の場合、申立人は任意後見人です。
まとめ
成年後見制度は、契約または申し立てにより家庭裁判所から選任された者が、ご本人の意思表示や日常生活の支援を行う制度です。
成年後見制度には、判断力の程度に応じて、補助、補佐、後見があります。
成年後見制度の利用に当たっては、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
後見制度は、ご本人の財産や身体を保護するための制度のため、申立人の考えどおりにはいかないことがあります。
後見人に弁護士や司法書士が選任された場合、報酬が必要になります。
成年後見制度には、判断力低下後に家庭裁判所に申し立てる法定後見と、判断力が低下する前に契約により後見人を定めておく任意後見があります。
成年後見手続きのサポートをしています
成年後見業務の経験を活かして、成年後見申立の手続きサポートを行っています。
弊所は千葉市若葉区にあります。成年後見をご検討の際はお気軽にご相談ください。
成年後見申立てサポート費用
| 業務の内容 | 報酬(税込み) | 実費 |
|---|---|---|
| 成年後見(後見、保佐、補助) 申立てサポート | 143,000円 | 実費として次の費用が別途必要になります 登記されていないことの証明書300円 医師の診断書作成料 家庭裁判所への申立費用代800円 法務局の登記手数料2,600円 予納切手代4~5,000円 鑑定が必要な場合は鑑定料5~10万円 |