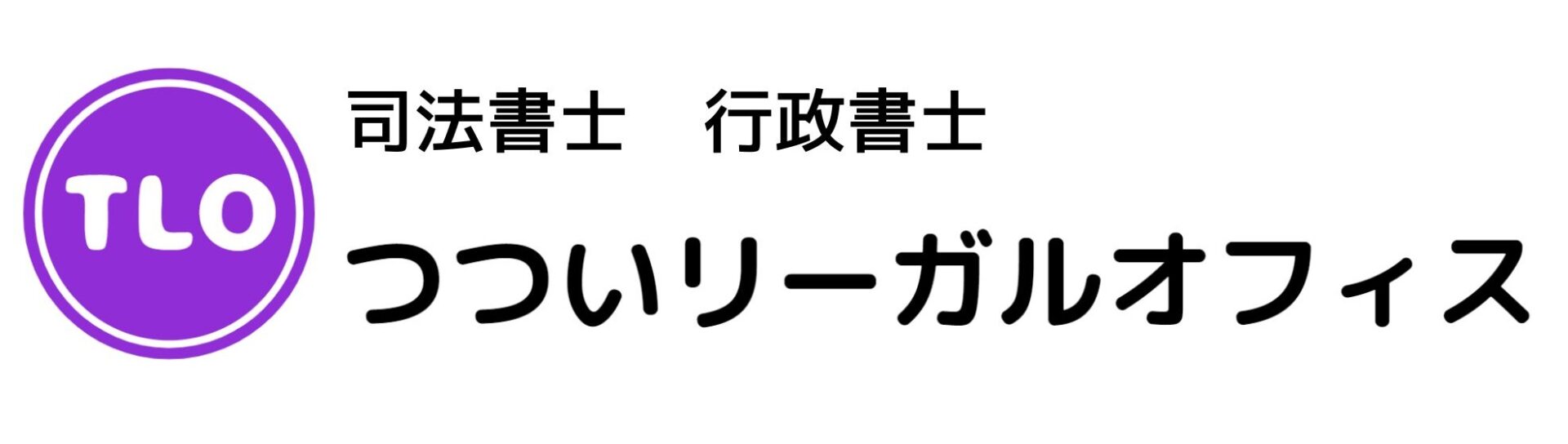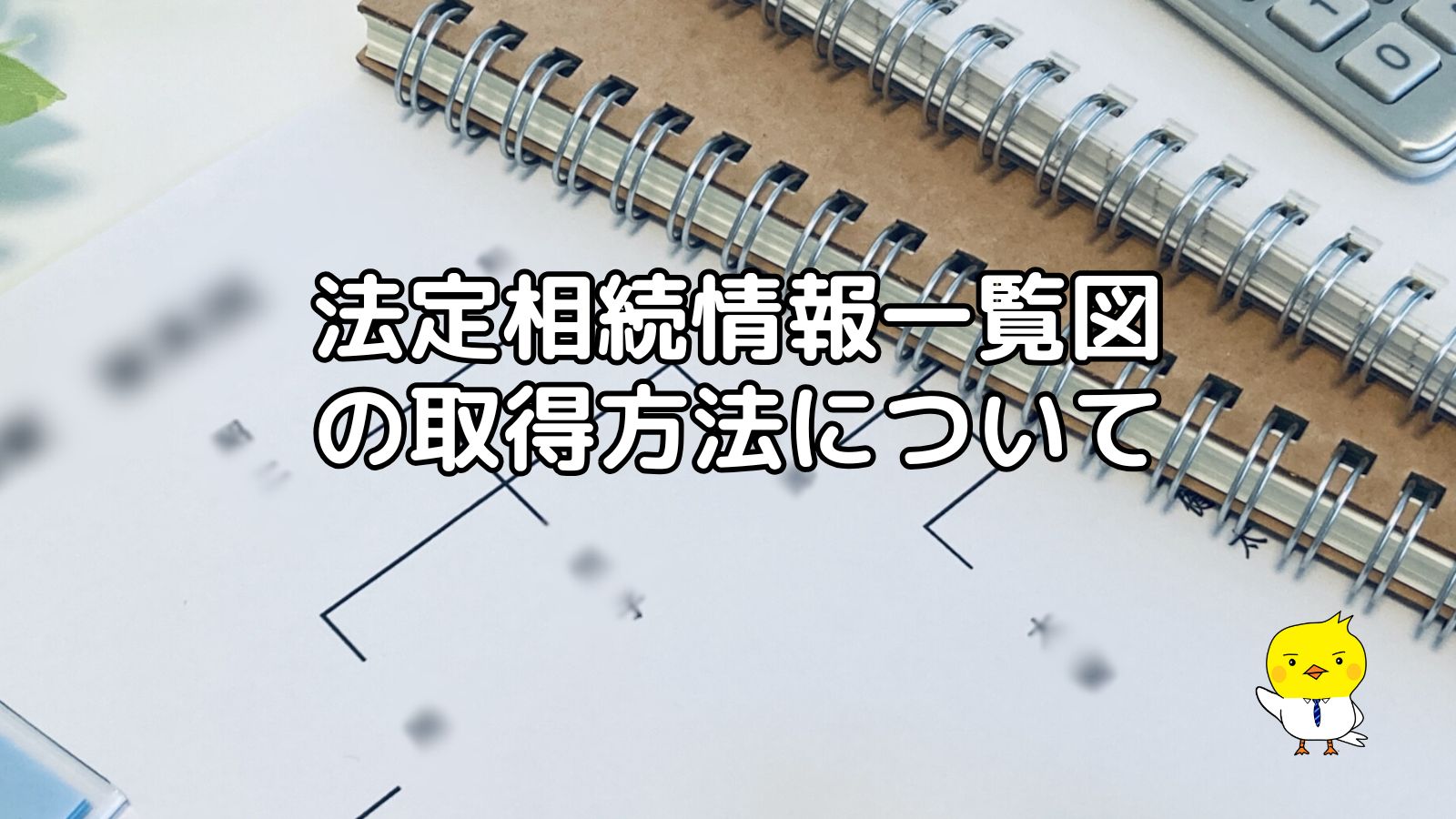法定相続情報一覧図の取得方法について
法定相続情報一覧図とは、相続の手続きの際に必要となる戸籍一式の代わりとして使用できる証明書であり、最近は金融機関などでその利用が推奨されています。
法定相続情報一覧図の取得方法について、千葉市の司法書士つついリーガルオフィスが解説します。
法定相続情報一覧図とは
相続手続には、お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人全員の現在の戸籍などの「戸籍の束」を相続手続きを行う機関ごとに提出する必要があります。
これらの戸籍の束の代わりになるものとして、法務局から法定相続情報一覧図の交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図の交付を受けることにより、戸籍の束を持ち歩く必要がなくなるため、戸籍は1通ずつ用意すれば足りることになります。
法定相続情報一覧図が必要な場合とは
法定相続情報一覧図が必要な場合とは、A銀行、B銀行、C証券会社および法務局など、相続手続を行う機関が多い場合です。
このような場合は、戸籍の束で対応するよりも、法定相続情報一覧図で相続手続きを行うことをおすすめします。
なお、法務局で相続登記を申請するだけなど、相続手続を行う機関が少ない場合は、手間と時間をかけてまで法定相続情報一覧図を取得する必要はありません。
法定相続情報一覧図取得のメリット・デメリット
法定相続情報一覧図を取得するメリットとして、次のようなものがあります。
①相続手続きを戸籍、除籍、原戸籍で行うと通数が多くなりますが、法定相続情報一覧図は1、2枚になります。
②相続手続き先で戸籍、原戸籍、除籍などの必要書類の一部が足りなかったというリスクを防止できます。
③法務局に相続登記を申請する場合、添付書類に法定相続情報一覧図の番号を記載することによって、戸籍や住民票の添付が不要になります。
※ただし、住民票の添付を省略できる場合には一定の条件があります。
デメリットとしては、次のようなものがあります。
①法定相続情報一覧図の取得にあたっては、お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続した戸籍、住民票の除票、相続人の戸籍、住民票など多くの書類を揃える必要があリます。
②法定相続情報一覧図の交付の申出書や法定相続情報一覧図の作成が必要になるなど、手続きが案外複雑です。
法定相続情報一覧図の取得方法
法定相続情報一覧図の取得は、法務局に交付の申出をして行います。
法定相続情報一覧図の交付の申出人
法定相続情報一覧図取得の交付の申出人は、お亡くなりになった方の相続人です。
しかし、お亡くなりになった方が日本国籍を有しない場合など、戸籍を提出することができない場合、法定相続情報一覧図の交付の申出をすることができません。
なお、法定相続情報一覧図の交付の申出は、代理人に依頼することができます。
法定相続情報一覧図の交付の申出先
法定相続情報一覧図の交付の申出は、次の市区町村を管轄する法務局に行います。
- お亡くなりになった方の最後の住所地
- お亡くなりになった方の本籍地
- 申出人の住所地
- お亡くなりになった方が所有する不動産の所在地
法定相続情報一覧図の交付の申出の必要書類
法定相続情報一覧図の交付の申出にあたっては、次の書類を準備する必要があります。
- お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍、原戸籍、除籍
- お亡くなりになった方の住民票の除票
- 相続人全員の現在の戸籍
- 申出人または代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードのコピー、住民票のいずれか)
- 法定相続情報一覧図の申出書
- 法定相続情報一覧図
- 代理人が申出する場合は委任状
- 代理人が親族の場合はその関係が分かる戸籍謄本、資格者の場合は身分証明書の写し等
- 法定相続情報一覧図に相続人の住所の記載をする場合は相続人の住民票
法定相続情報一覧図申出書の作成
戸籍や住民票の除票が揃いましたら、法定相続情報一覧図申出書を作成します。
法定相続情報一覧図申出書の記載方法は、次のように行います。
- 被相続人の表示
-
住民票の除票、戸籍を参考に、お亡くなりになった方の最後の住所、氏名、生年月日、死亡年月日を記入します。
- 申出人の表示
-
申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄を記入します。
住所や氏名は、免許証やマイナンバーカード、住民票の記載と一致している必要があります。
- 代理人の表示
-
代理人によって申出する場合は、代理人の住所、氏名、連絡先を記入し、申出人との関係にチェックをします。
- 利用目的
-
法定相続情報一覧図を使用する目的にチェックします。(複数チェック可)
- 必要な写しの通数・交付方法
-
提出する金融機関、法務局の数などに応じて必要な通数を記入します。
次に交付方法を選びます。
郵送による交付を希望する場合は、角2号の封筒に切手を貼ったもの、またはレターパックを同封します。
- 被相続人名義の不動産の有無
-
お亡くなりになった人の所有する不動産の有無、不動産を所有している場合は不動産の所在・地番・家屋番号または不動産番号を記載します。
- 申出先登記所の種別
-
該当する内容にチェックを入れます。すべてに該当する場合は、すべてチェックをします。
※被相続人名義の不動産の所在地にチェックをした場合、先の被相続人名義の不動産の有無と一致するように注意しましょう。
法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図の作成方法について解説します。
法定相続情報一覧図には、お亡くなりになった方とその相続人(代襲相続人を含む)、続柄を記載します。
相続開始前にすでにお亡くなりになっている方は記載できないなど、作成にあたっては一定のルールがありますので注意が必要です。
法務局のホームページから、相続に合った様式を選択して作成すると便利です。
※用紙に記載可能な範囲がありますので、注意して作成します。

結構手間のかかる、難しい手続きかもしれません。
法定相続情報一覧図の取得に要する費用
法定相続情報一覧図の交付を受けるにあたって、法務局に納める手数料等はありません。
法定相続情報一覧図の再交付の申出方法
法定相続情報一覧図は5年以内に限り、再交付を受けることができます。
法定相続情報一覧図の再交付の申出人
法定相続情報一覧図の再交付の申出を行うことができるのは、最初の法定相続情報一覧図の交付の申出をした申出人です。
法定相続情報一覧図の再交付の申出先
再交付の申出は、最初に法定相続情報一覧図の交付の申出をした法務局に行います。
法定相続情報一覧図の再交付の申出の必要書類
法定相続情報一覧図取得の再交付の申出にあたっては、次の書類を準備する必要があります。
- 申出人または代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードのコピー、住民票のいずれか)
- 法定相続情報一覧図の再交付の申出書
- 代理人が申出する場合は委任状
- 代理人が親族の場合はその関係が分かる戸籍謄本、資格者の場合は身分証明書の写し等
法定相続情報一覧図の有効期限
法定相続情報一覧図の有効期限は、その提出先によって異なります。
金融機関に提出する場合は、発行日から6か月以内の場合が多いです。有効期限が切れた場合は、法定相続情報一覧図の再交付の申出を行う必要があります。
法務局で登記申請に使用する場合、有効期限の定めはありません。
まとめ
法定相続情報一覧図とは、相続手続きに必要な戸籍、原戸籍、除籍の代わりとして使用できる書面です。
相続手続きを行う先が多い場合は、法定相続情報一覧図を取得するのが便利です。
法定相続情報一覧図の取得にあたっては、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍、原戸籍、除籍、相続人全員の戸籍、法定相続情報一覧図申出書や法定相続情報一覧図など多くの書類が必要になります。
相続手続きをサポートしています
法定相続情報一覧図の取得はご自身でもできますが、司法書士に依頼すると煩わしい手間をかけることなく、法定相続情報一覧図を迅速に取得することができます。
千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスでは、法定相続情報一覧図の取得など、相続手続き全般のサポートを行っています。