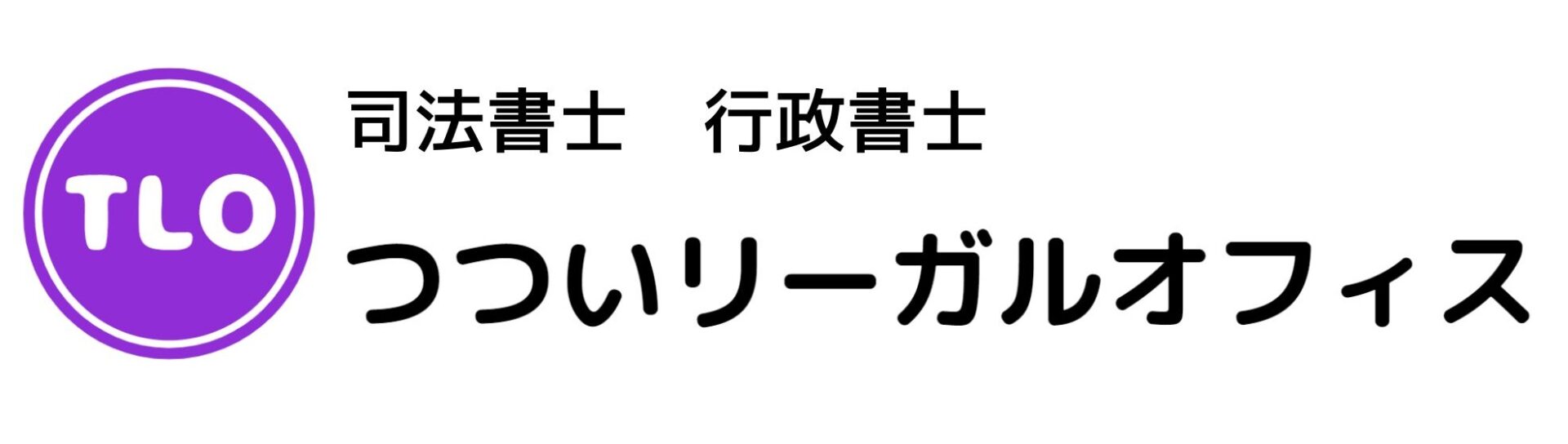相続土地国庫帰属制度について
令和5年4月27日から、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属制度)が施行されました。
相続土地国庫帰属制度について、千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスが解説します。
相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度とは、法務局に申請することにより、相続した一定の要件を満たす土地を国に引き渡すことができる制度です。
被相続人から相続した使う予定のない土地や、田畑、山林で売却できない土地、管理の難しい土地が相続土地国庫帰属制度の利用を検討する土地になります。
相続土地国庫帰属制度が利用できない土地について
相続土地国庫帰属制度は、全ての土地について利用できるわけではありません。
国に過大な管理費用や労力が生じてしまう可能性のある土地は、相続土地国庫帰属制度の対象外とされています。
具体的には、次のような土地になります。
却下要件(その事由があれば却下となるもの)
次のような土地は、申請しても却下になります。
- 土地上に建物がある
- 土地に抵当権などの担保権が登記されている
- 他人による使用が予定されている土地(通路、墓地、境内地などで利用)
- 崖地または産業廃棄物の埋まっている土地
- 境界が明らかではない又は所有権が誰か、境界がどこかについて争いがある
※境界は、筆界を指すものではないため、土地の測量までは必要ありませんが、争いがあれば申請は却下になりますので注意が必要です。
不承認要件(費用、労力がかかりすぎるとの判断により不承認となるもの)
次のような土地は、申請しても不承認となります。
- 勾配が30度以上でかつ5メートル以上の高さの崖がある土地で、管理に多くの費用や労力を有するもの
- 土地の管理を妨害する工作物、車両、樹木その他の有体物がある土地
- 管理するにあたって除去しなければならない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地所有者と裁判をしなければ管理又は処分することができない土地
- 通常の管理又は処分をするために多くの費用や労力が必要な土地
相続土地国庫帰属制度の手続きについて
相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、不動産所在地の管轄の法務局に国庫帰属承認申請を行う必要があります。
国庫帰属承認申請の申請人
申請人は、当該土地を相続した相続人、または遺贈を受けた相続人です。
※相続人以外の第三者は不可
弁護士、司法書士、行政書士は、申請書類等の代理作成を行うことができます。
国庫帰属承認申請の提出先法務局
申請先は、土地の所在地を管轄する法務局の本局にある相続土地国庫帰属制度担当部署になります。
※各都道府県内に1庁となります。
申請にあたっては、申請書および添付書類を添えて、窓口又は郵送で提出する方法により行います。
国庫帰属承認申請の必要書類
おもな必要書類は、次のとおりになります。
- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする書面
- 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 土地の形状を明らかにする写真
- 申請者の印鑑証明書
国庫帰属承認申請手続きの流れ
- 必要書類の収集、作成を行います。
- 法務局に承認申請書の提出、審査手数料の納付を行います。
- 法務局の担当者が書面審査や現地の調査を行います。(千葉県内の土地の場合は8か月以上)
※引き取ることができない土地の場合は、却下または不承認となります。 - 承認された場合は承認通知および負担金通知がされます。
- 30日以内に負担金を納付します。
- 国庫帰属した旨の登記がされます。
国庫帰属承認申請に要する費用について
国に審査手数料として、土地1筆当たり1万4,000円を納める必要があります。
あわせて、10年間分の土地管理費用として、土地の地目や面積に応じて負担金20万円〜の納付が義務付けられます。
司法書士などの専門家に手続きを依頼する場合は、報酬も別途必要になります。
まとめ
相続した土地の売却や管理が困難な場合は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討しましょう。
相続土地国庫帰属制度が利用できる土地には一定の条件があり、却下や不承認となる土地が定められています。
国庫帰属承認申請から承認まで、8か月以上(千葉県の場合)の時間がかかります。
承認された場合は、30日以内に負担金を納付する必要があります。