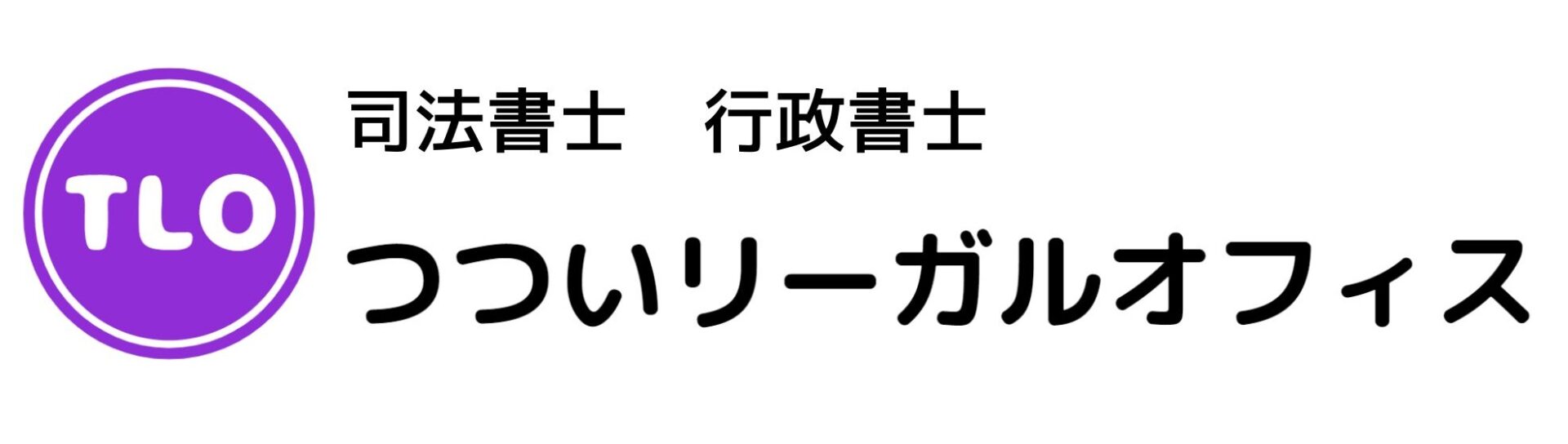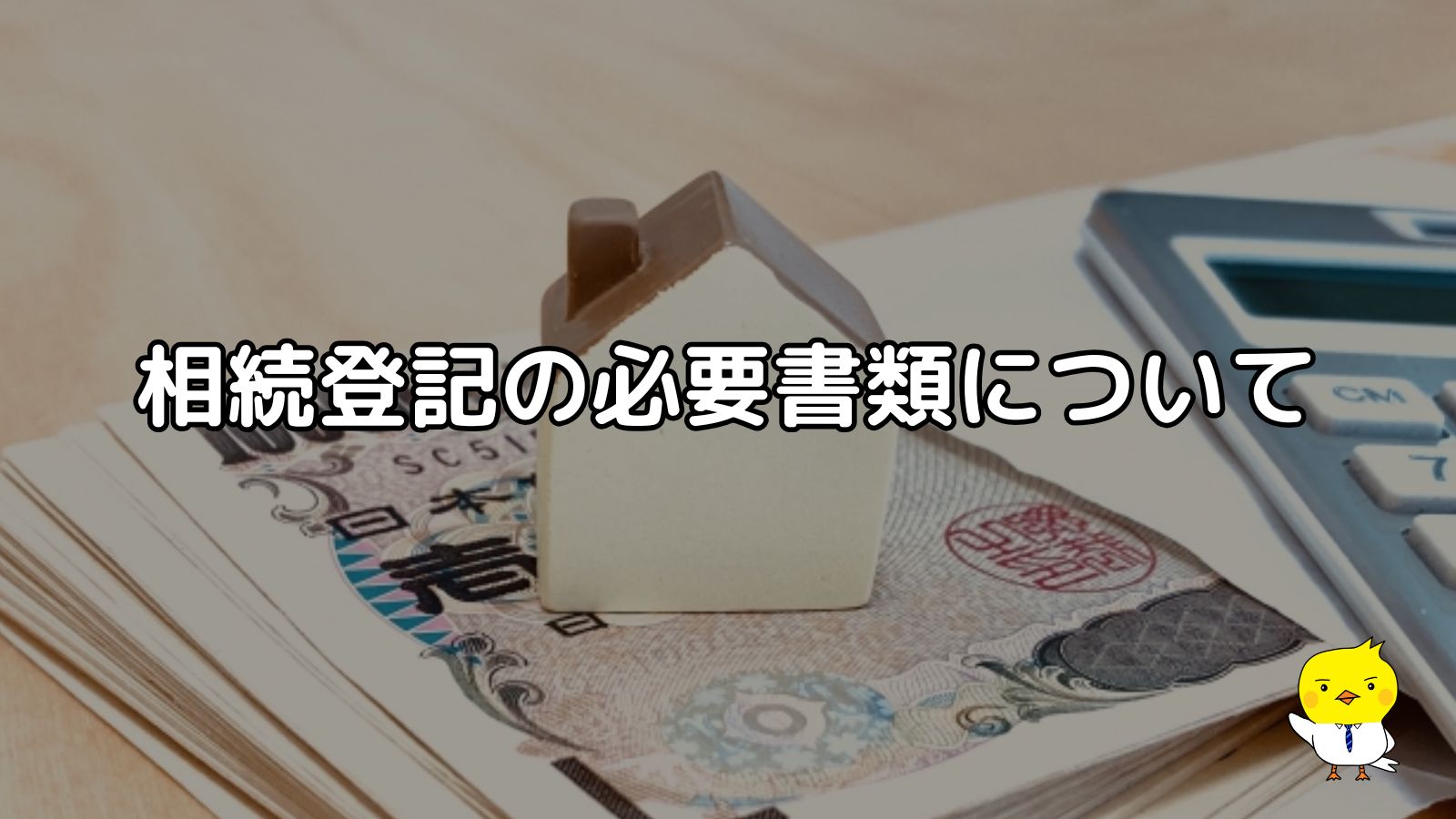相続登記の必要書類について
相続財産に不動産がある場合は、不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記の申請を行う必要があります。相続登記に必要な書類について、千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスが解説します。
相続登記の必要書類について
法務局における相続登記には、次のような書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍、原戸籍、除籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 不動産の固定資産税明細書または固定資産税評価証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 相続財産の分割方法等に関する書面
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続関係説明図
- 相続の所有権移転登記申請書
詳細について次に解説します。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、原戸籍、除籍
被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍、原戸籍、除籍を本籍地の市区町村役場に請求します。
戸籍、原戸籍、除籍の収集に当たっては、次の点に注意が必要です。
・遠隔地の市区町村役場に郵送で請求する場合は、返送用封筒にあわせて、手数料分の定額小為替を郵便局で購入のうえ同封する必要があります。
※定額小為替の購入に際しては、額面にかかわらず1枚につき200円の手数料が必要になります。
・転籍や、婚姻により他の市区町村に本籍移した場合は、それぞれの市区町村役場に請求する必要があります。
・戸籍の請求にあたっては、収集すべき戸籍の本籍地や筆頭者を確認するため、戸籍を読み解く必要があります。手書きで作製された昔の戸籍は、判読が困難なものもあります。
なお、令和6年3月1日から、戸籍の広域交付制度が開始されています。
他の市区町村に保管されている被相続人の戸籍、原戸籍、除籍もお近くの市区町村役場で収集することができるようになりました。
※一部の古い戸籍や戸籍の附票など、取得できない書類もあります。
相続人の戸籍全部事項証明書
被相続人がお亡くなりになった日以降に取得した相続人の戸籍全部事項証明書を収集します。
※被相続人がお亡くなりになる前に取得した戸籍全部事項証明書は使用することができません。
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
法務局の登記簿に記載されている被相続人の住所と、被相続人の最後の住所が異なる場合は、住所のつながりを証する書面が必要です。
また、本籍と最後の住所が異なる場合も、本籍と最後の住所が記載されている書面が必要です。
これらを証する書面として、本籍地の記載ある住民票の除票または戸籍の附票を収集します。
なお、上記書面を収集しても登記簿に記載されている住所の記載ある書面が入手できないときは、権利証や不在籍、不在住証明書を準備する必要があります。
※法務局における相続登記では、上記書面の用意が非常に難しく皆さんが苦労する部分になります。
※長期間相続登記を放置している場合は、上記書面の入手が困難な場合があります。
相続登記する不動産の固定資産税明細書または固定資産税評価証明書
法務局に納める登録免許税は、固定資産税評価額から算出するため、本年度の納税通知書にある固定資産税明細書又は市区町村役場で評価証明書を取得します。
※これらの書類は、原則としてコピーを申請書に添付する必要があります。
不動産を相続する相続人の住民票
相続により不動産を取得する相続人の住民票が必要になります。
※住民票に有効期限はありません。
相続財産の分割方法等に関する書面
相続財産は、民法第900条により法定相続分に応じて相続人全員で引き継ぐのが原則です。
しかし、不動産を相続人全員で引き継ぐより、特定の相続人が引き継ぐケースが多いです。
不動産を特定の相続人が引き継ぐ場合は、内容に応じて次の書面を準備する必要があります。
※一般的には遺産分割協議書を作成することが多いですが、これらの書面の作成が一番難しい作業になります。
1 遺産分割協議書
特定の遺産を、相続人全員の協議により特定の相続人が相続することとした場合、例えば相続人A、BのうちAが不動産を相続とするとした場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
2 相続分譲渡証明書
相続人は、遺産分割協議が成立するまでは、自分の相続分を他人に譲渡することができます。
相続分を譲渡した相続人は、相続分譲渡証明書を作成します。
3 特別受益証明書
生前に、相続分に相当する遺産を贈与されていた場合や遺贈を受けていたときは、相続分がない旨の特別受益証明書を作成します。
相続人の印鑑証明書
遺産分割協議書を作成した場合は、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
相続分譲渡証明書、特別受益証明書を作成した場合は、当該相続人の印鑑証明書が必要になります。
相続関係説明図
法務局に戸籍、原戸籍、除籍の原本を提出すると登記完了後も返却されません。
戸籍をほかで使う必要があるときは、これら全ての戸籍、原戸籍、除籍のコピーを取って添付するか、相続関係説明図を作成します。
相続関係説明図は、被相続人の情報や、相続人全員の情報を記載します。
相続関係説明図の作成にあたっては、遺産分割協議により不動産を相続する相続人の氏名の前に(相続)、相続しない相続人の氏名の前には(分割)と記載する必要があるなど一定のルールがあります。
相続登記申請書
相続登記には、相続登記申請書を作成する必要があります。
相続登記申請書には、申請人が押印します。
登記申請書が複数枚になる場合は、綴り目に契印を行います。
押印および契印は実印でなくても構いませんが、手続き完了後、窓口で書類を受け取る際に相続登記申請書に押印したハンコが必要になりますので、どのハンコで押印したか忘れないように気を付けましょう。
登記申請書の記載に間違いがあると、法務局から訂正のために来庁するよう連絡が来ます。
次の記載に間違いがないか慎重に添付書類と照合して確認しましょう。
- 被相続人の死亡日
- 被相続人の氏名
- 不動産を相続する相続人の住所・氏名、持分がある場合はその割合
- 相続する不動産を管轄する法務局
- 課税価格と登録免許税額
- 不動産の表示
まとめ
- 相続登記には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、原戸籍、除籍などが必要になります。
- 法定相続による場合以外は、遺産の分割方法等に関する書類を作成する必要があります。
- 相続財産に不動産がある場合は、法務局に相続登記を行う必要があります。
- 遺産分割協議書や相続登記申請書など、内容を正確に記載した書類の作成が必要です。
相続登記手続きをサポートします
相続登記には、多くの収集書類と、内容を正確に記載し作成した書面が必要になります。
法務局への申請は、不動産の所在地を管轄する法務局のみでしか受け付けていないうえ、申請に関する細かい取り決めがあります。
ご自身で手続きを進められると、手続きのことで不安になったり、途中でわからなくなってしまうかもしれません。
千葉市若葉区の司法書士行政書士つついリーガルオフィスでは、お客様が安心してお任せいただけるよう、迅速に手続きを進めるためのサポートや法的アドバイスを行っています。
お気軽にご相談ください。