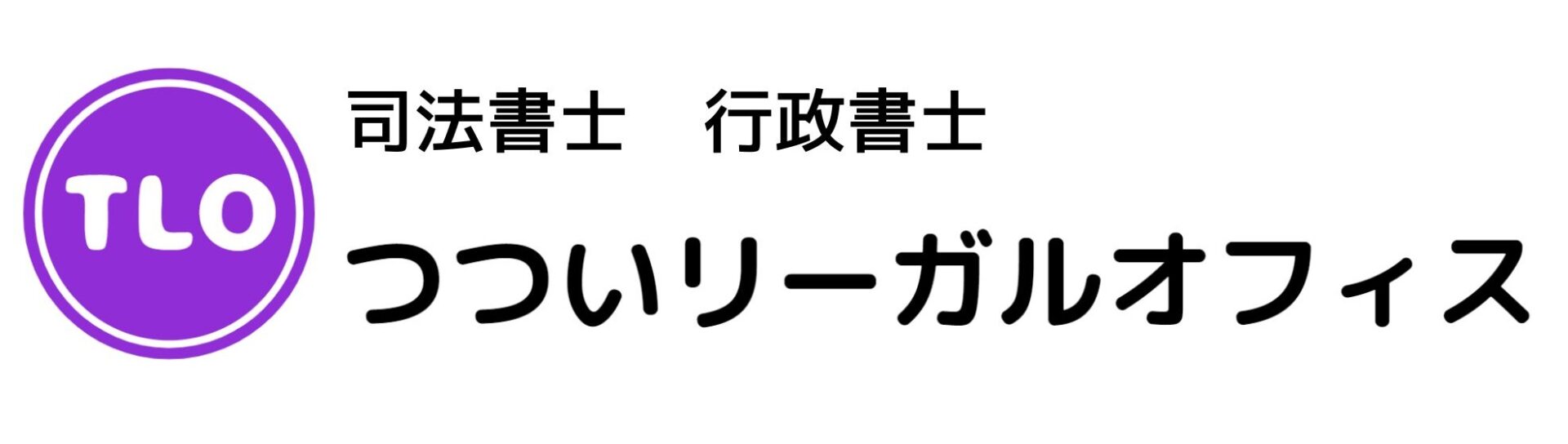法務局における相続登記申請から完了までの流れ
相続登記に必要な書類が準備できましたら法務局に相続登記の申請を行います。法務局における相続登記の申請から登記完了までの流れについて、千葉市若葉区の司法書士つついリーガルオフィスが解説します
相続登記の申請場所は?
相続登記は、不動産の所在地の市区町村を管轄する法務局の本局・支局・出張所に申請する必要があります。
法務局の管轄は、「○○市 法務局 管轄」で検索することにより、インターネットで調べることもできます。
同じ市でも町ごとで管轄が分かれていることもありますので、管轄法務局を間違えないように気を付けましょう。
※相続登記を申請する法務局を間違えると、申請は取下げまたは却下になります。
原本還付について確認しましょう
相続登記の申請にあたって、法務局に戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票などの書類を提出する場合は原本の提出が原則です。
原本の返却を希望する場合は、原本還付の処理を行なう必要があります。
原本還付処理の方法:返却を受けたい書類を1部コピーのうえ、末尾に「原本に相違ない 申請人氏名」と記載し、押印します。
※原本が複数枚になる場合は、左側をホチキスで留めて各ページの綴り目に契印します。
※裏面が白紙でない書類は、両面のコピーが必要になります。

綴り目の契印は図のように行います。
契印は申請人が行います。
相続登記の申請方法
相続登記の申請は、管轄法務局の窓口で直接、または郵送で申請します。
オンライン申請もありますが、専用ソフトのインストールや、電子署名の付与が必要になるので、手間がかかります。
相続登記を郵送で申請する場合の注意点
郵送により相続登記を申請する場合、郵送する郵便の種類については次のように定められています。
不動産登記規則第53条
登記の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
2前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に不動産登記申請書が在中する旨を明記するものとする。
つまり、相続登記申請を郵送により行う場合は、書留郵便またはレターパックプラスで「不動産登記申請書在中」と記載のうえ管轄法務局に送付する必要があります。
相続登記申請したら行うこと
登記の完了予定日を確認する
窓口で申請する場合は、受付に「権利登記の完了予定日」が掲示されていますので確認します。基本的には受付の際に、担当者が口頭で教えてくれます。
郵送で申請する場合は、法務局のホームページに完了予定日が掲載されていますので、管轄法務局の完了予定日を確認します。
※郵送の場合は、書類が法務局に到達した日に対応した完了予定日になりますので注意が必要です。
※補正がある場合は、補正完了時に改めて完了予定日が決まることになります。
法務局における提出書類の審査
法務局では、申請書や遺産分割協議書など提出された書類に誤りがないか審査します。
無事に審査が通れば登記簿に新しい所有者が記入されますし、訂正箇所があれば補正の連絡が来ます。
もし法務局の担当者から電話で連絡が来た時は、速やかに補正に対応しましょう。
※ご自身で相続登記を申請される場合は、法務局から連絡が来る確率が高いとお考え下さい。
※遠方の法務局に申請して、補正ができない場合は、申請が却下される可能性がありますのでご注意ください。
法務局から何も連絡が無ければ手続きが無事進んでいますので、完了予定日以降に書類を受け取ることになります。
相続登記手続きが完了したら
登記が無事完了すると、相続人のために新しい権利証(登記識別情報)が交付されます。
※申請時にメールアドレスを提供した場合に限り、法務局から通知があります。
相続登記の完了書類を窓口で受け取る場合
新しい権利証や、提出した書類を受け取るために、申請書に押した印鑑と身分証明書を持って窓口に行く必要があります。
登記識別情報通知は、相続人1人および不動産1つにつき1通ずつ交付されます。
相続登記の完了書類を郵送により受け取る場合
郵送で受け取る場合は、相続登記申請時に次のような手続きをとる必要があります。
不動産登記規則第55条
4 前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。
一申請人等が自然人である場合において当該申請人等の住所に宛てて書面を送付するとき、又は申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき(第三号に掲げる場合を除く。)日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
6 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、送付に要する費用を納付しなければならない。
つまり、相続登記の受け取りは相続の申請時に、本人限定受取郵便の処理をした封筒および切手を提出します。
※本人限定受取郵便は、郵送料を郵便局のホームページでご確認のうえ、多めに切手を用意するようにしましょう。
※料金不足の場合は、追加の切手を送付するように法務局から補正を求められます。
※定型の封筒は、権利証や戸籍などの書類が入りきらないことがありますので、定型外の角2号封筒を用意しましょう。
法務局から返却を受けた書類の取り扱いについて
- 登記識別情報通知は、再発行されないため、紛失しないように保管しましょう。
- 遺産分割協議書は印鑑証明書と一緒に保管しておきましょう。
- 戸籍一式もそのまま保管しておきましょう。
- 登記完了証は、登記が終わったことを法務局が証明する書面です。特に保存は不要です。
まとめ
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請する必要があります。
原本の返却を求める場合は原本還付の処理が必要になります。
相続登記は、管轄法務局の窓口に持参または書留やレターパックプラスによる郵送により申請します。
郵送で書類の返却を求める場合は、申請時に本人限定受取郵便の処理をした封筒と多めの切手を同封する必要があります。
相続手続きをサポートします
相続登記を法務局に申請するのは、相続登記手続きの中でも一番難しい手続きです。
司法書士にお任せいただければ、法務局に相談・申請・補正に行くことなく相続手続きが完了します。
司法書士つついリーガルオフィスでは、お客様が安心してお任せいただけるよう、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
電話、メール、LINEでお気軽にご相談ください。